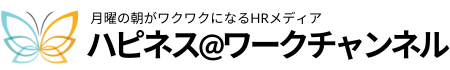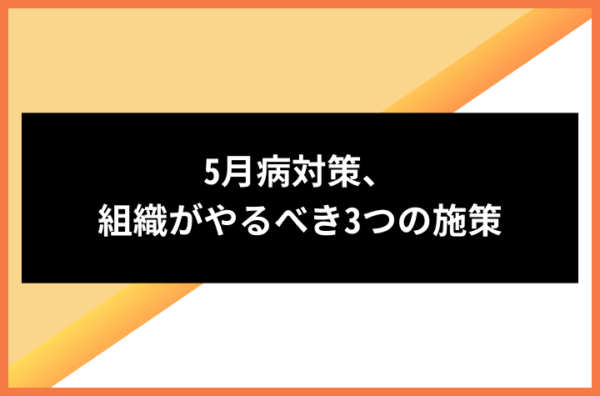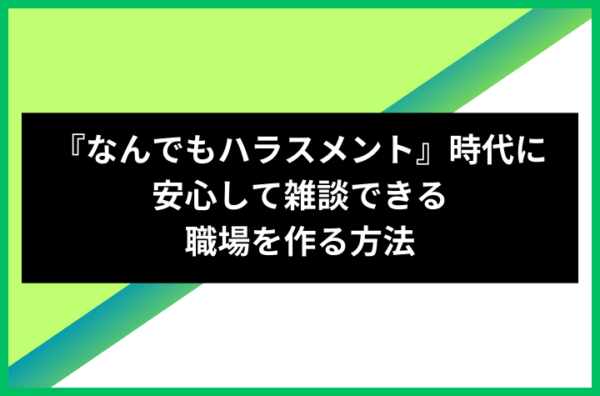『なんでもハラスメント』時代に安心して雑談できる職場を作る方法
目次
近年、どんな言動も『なんでもハラスメント』に繋がりかねない時代が到来しました。「最近どう?」と気軽に声をかけることすら、ハラスメントになりかねない恐怖に駆られている管理職も多いのではないでしょうか。しかし、『なんでもハラスメント』を防ぐには、コミュニケーションを避けることが最善ではなく、適切な会話術を身につけることが職場の信頼関係を築くための第一歩です。本記事では、『なんでもハラスメント』と化す前に、管理職が知っておくべき安全な雑談のコツを紹介し、ハラスメント防止のためにできることをお伝えします。困った時のちょっとした知恵袋として、本記事をご活用ください。
こんな人におすすめ!
- 部下との雑談や声かけすら怖くなっている管理職
- 組織文化として心理的安全性を高めたい人事担当者
- ハラスメントのリスクを防ぎたい経営者
1.『なんでもハラスメント』時代に管理職が感じる不安
現代の職場では、ちょっとした一言が思わぬトラブルを引き起こすことがあります。特に管理職は、その微妙なバランスに悩むことが多く、何がハラスメントと見なされるのか判断に困ることもあるのではないでしょうか。日常的な言葉ですら、思いがけず地雷になる可能性があることを考えると、その不安は計り知れません。なぜ、そんな状況が生まれたのでしょうか。
1-1. 日常会話すら地雷に?!『最近どう?』がハラスメントになる現実
何気ない「最近どう?」の一言が、ハラスメントと受け取られる――そんな『なんでもハラスメント』が職場に広がる今、管理職やリーダーは無意識のうちに加害者扱いされる危険と隣り合わせです。ちょっとした声かけがトラブルやクレームに発展する事例も増え、「何を言えばいいのか分からない」と思う管理職は、必要なコミュニケーションさえ避けるようになります。特に価値観の異なる世代間では、わずかな言葉の行き違いが大きな誤解を生み、日常会話すら“地雷”となる現実が待っています。このままでは職場の空気が冷え込み、信頼関係さえ崩れかねません。
1-2.『なんでもハラスメント』になってしまう原因とは
『なんでもハラスメント』と捉えられてしまう背景には、根本的なコミュニケーション不足に加え、“言い方”や“伝え方”の問題があります。上司からの何気ないアドバイスや雑談も、関係性や場面を誤れば「おかしい」「不快」と受け止められる時代です。かつて、昭和の時代では当たり前だった、人前での叱責や厳しい口調が指導の一環とされていましたが、今ではそれが「パワハラ」とされるケースも少なくありません。信頼関係が希薄な状態では、たとえ善意でも言葉は表面的に受け取られ、ネガティブな解釈に傾きやすいのです。さらに世代間の価値観の違いや多様性の広がりも影響し、「普通」「常識」とされてきた振る舞いが誤解を招くことも増えています。だからこそ、日頃からオープンな対話の場を作り、相互理解を育む“土壌づくり”が重要なのです。
1-3.ビジネスパーソンの約70%が、コミュニケーションに「課題がある」
エン・ジャパンが2024年に実施した調査によると、上司・部下間のコミュニケーションに「課題がある」と感じているビジネスパーソンは約70%に上ります 。特に上司側は「相手との精神的な距離を感じる」(40%)、部下側は「指示・指導がわかりづらい」(48%)といった具体的な悩みを抱えており、双方の認識のズレが浮き彫りになっています。このような背景から、上司が部下に対して「最近どう?」といった何気ない声かけをする際にも、その距離感やタイミングを慎重に考慮しなければ、意図しないハラスメントと受け取られるリスクがあるのです。特に、価値観やコミュニケーションスタイルが異なる世代間では、些細な言動が誤解を招きやすく、管理職やリーダーが無意識のうちにハラスメントの加害者とされる可能性も否定できません。
2.『なんでもハラスメント』に繋がる“話さないリスク”
このセクションでは、コミュニケーションを避けることによって生じるリスクを探ります。話さないことが何をもたらすのかを理解し、健全な職場環境を維持するためのヒントを提供します。
2-1.管理職がコミュニケーションを避ける理由
「何を言ってもハラスメントになるかもしれない」という恐れから、管理職が部下とのコミュニケーションを避ける傾向が強まっています。過去には当たり前だった叱責や指導も、今では「おかしい」「不快だ」と感じる人が増え、どの言動が“地雷”になるかわからない不安が管理職を萎縮させています。特に昭和型のマネジメントを経験してきた世代にとって、「何が正解なのか分からない」状況は大きなストレスです。しかし、無言でいることは職場の信頼不足を招き、部下の不安や不満を助長します。大切なのは“何を伝えるか”だけでなく“どう伝えるか”。一方的な命令や叱責ではなく、個別の対話や傾聴、相手の立場に立った伝え方が求められています。コミュニケーションを避けることは、結果的に『なんでもハラスメント』のリスクを高める皮肉な結果につながるのです。
2-2.相談しにくい職場が『なんでもハラスメント』を生む
『なんでもハラスメント』を恐れて管理職が沈黙を選ぶと、職場には「相談しにくい空気」が生まれます。上司から話しかけられない、雑談がない。そんな職場では、部下も「困ったときに相談していいのかわからない」と感じやすくなるのです。たとえ問題が起きても、声を上げるきっかけがないまま、悩みが表面化しない“隠れたハラスメント”が進行するリスクがあります。信頼関係が築けていない状態では、「助けてほしい」という声も上司に届きません。結果として、小さなトラブルが放置され、大きな問題に発展する可能性が高まります。管理職が「話さない」という選択をすることで、部下に“孤立”という形の負担を強いることになるのです。
2-3.『なんでもハラスメント』を恐れ“話さない”ことが最大のリスク
『なんでもハラスメント』を恐れて無言でいることは、実は最も危険な選択肢です。コミュニケーションの欠如は、職場での信頼関係や心理的安全性を脅かします。誰もが“本音を言えない”空気は、結果的に誤解や不満を積み重ね、組織全体を不健全にしていきます。表面上は問題がないように見えても、水面下では不信感が広がり、突然の離職や訴えという形で表れることもあります。管理職の立場にある人材に求められるのは、「話さない」という萎縮ではなく、リスクを考慮しつつセクハラ防止など具体的対策を踏まえた安全なコミュニケーションの実践です。日頃から「相談していい」「話していい」というメッセージを発信し続けることで、信頼の土台は育ちます。無言ではなく“意識的な対話”こそが、職場を守る鍵になるのです。
3.『なんでもハラスメント』を避けるための線引きガイド
「これぐらいは大丈夫だろう」と軽い気持ちで行った言動が、おかしいと感じる人がいることで、意図せずハラスメントになってしまうこともあります。この章では、実際に起こり得るコメント事例を交えながら、『なんでもハラスメント』を避けるための具体的な線引きについて解説します。
3-1.これはセーフ!安全な雑談例
●共通の話題から会話を始める
どんな人にも共感できる天候や季節の話題は、会話を和やかにし、誰もが安心して参加できるようにします。
例:「今日は過ごしやすいですね」「桜が咲き始めましたね」
●具体的なフィードバックで相手を褒める
曖昧な褒め言葉ではなく、具体的な成果や仕事ぶりに触れることで誠意が伝わり、相手に好印象を与えます。
例:「〇〇さんが作成した資料、非常に分かりやすかったです」
●相手の関心に配慮した話題を選ぶ
相手が興味を持つ話題に寄り添うことで、自然な会話が生まれます。無理に深掘りせず、相手の反応を見ながら会話を進めましょう。
例:「最近〇〇の映画が話題ですね」「昨日の試合は〇〇のチームが勝ちましたね」
3-2.気を付けたいグレーゾーン!誤解されやすい微妙な言動
●外見に関する言及は慎重に
相手の捉え方次第ではハラスメントに該当する、しないが変わります。一度なら好意的でも、繰り返しだと外見評価が負担になることがあります。
例:「かわいいね」「きれいだね」「今日の服、似合ってるね」
●プライベートに踏み込みすぎない
相手のプライベートな情報を過度に尋ねることは、圧力を感じさせる原因となり得ます。相手が話したがらない様子であれば、無理に質問しないよう配慮しましょう。特に恋愛や結婚などの話題を何度も聞くことは、詮索やプライベート侵害と捉えられることもあります。
例:「結婚しないの?」「2人目の子どもはまだ?」
●冗談や評価が誤解を招くことがある
冗談や主観的な評価は、人によって受け取り方が異なるため、冗談のつもりでも、相手にとっては名誉を傷つけたり恥をかかせる行為だと不快に感じる場合もあります。
例:(他の社員の前で冗談交じりに)「できないやつだな」「こんな仕事、普通〇時間で終わるでしょ」
3-3.これは完全にアウト!即NGのハラスメント言動
●服装や容姿、身体的特徴についての発言
他人の容姿を揶揄することは深刻なハラスメントです。
例:「今日は肌荒れひどくない?」「最近太ったんじゃないの」「スカートが短くて色っぽいね」「いつもより化粧が濃いよね」など
●性的なからかいやわいせつな発言
性的な冗談や発言は、相手が不快に感じるだけでなく、セクシュアルハラスメントとして法的に問題となります。また、職場に性的な特徴を誇張したフィギュアを飾ったりすることも、周囲が不快と感じたらハラスメントとなりえます。
例:「生理だから機嫌悪いの?」「スリーサイズ教えてよ」「触ったって減るもんじゃないでしょ」など
●差別的な言動やプライベートに踏み込んだ発言、執拗な誘い
人種、性別、出身地、学歴などに関する差別やプライベートな情報の無断暴露、執拗な誘いは、重大なハラスメントに該当します。相手の尊厳を守ることが重要です。
例:「〇〇出身だから仕方ないね」「彼氏(彼女)いるの?」「デートしようよ」「俺のこと気になってるんでしょ」など
4.『なんでもハラスメント』を防ぐコミュニケーションのテクニック
前章では、「どのような話題がセーフで、どのような言動がグレー・アウトになるのか」を具体的に示しました。しかし、「どんな話題を選ぶか」だけでは安全なコミュニケーションは成立しません。同じ話題でも「どのように話すか」「どんな姿勢で接するか」によって、相手の受け取り方が大きく変わります。ここでは、相手が安心して雑談に参加でき、誤解されにくい関係を築くための「話し方」「聞き方」の基本スキルを解説します。
4-1. 「傾聴」と「観察」の重要性
「何を話すか」を決める前に大切なのは、「相手をよく見る・よく聞く」ことです。
相手が今どんな状態なのか、話す準備ができているのか、会話を楽しめているのか――こうした「非言語的なサイン」に気づくことで、自然で無理のない雑談につながります。
たとえば、忙しそうにしている相手に冗談を飛ばせば、軽い会話のつもりでも「空気を読めない人」と思われてしまうこともあります。
逆に、疲れている様子に気づき「大丈夫ですか?」と声をかければ、相手に寄り添うコミュニケーションになります。
●ポイント
相手の表情・声のトーン・姿勢などを観察する
相手が話すペースに合わせる
話を途中で遮らない
「聞く」「見る」という基本行動ができると相手の心理的安全性が高まり、この人は分かってくれると信頼につながります。
●例
✕「最近どう?元気?」(相手が疲れた表情なのに無理に話しかける)
〇 「お疲れ様です。ちょっと忙しそうですね」(様子を気遣う一言と相手の状態を汲み取った声かけ)
4-2.「オープン質問」で自然に会話を広げる
雑談でありがちなのは、「YES / NO」で答えが終わる質問を繰り返してしまい、会話が続かないケースです。「会話が続かない=相手が話したくない」と誤解しがちですが、実は質問の仕方に原因があることも多いことも。ここで効果的なのが、自由に答えられる質問形式です。「どう思いますか?」「どんな感じでしたか?」といった問いかけは、自分の言葉で答えやすい雰囲気を作ります。
●ポイント
「どんな」「どう」などの問いかけを意識する
相手の立場や体験に寄り添う質問を心がける
「決めつけ」「誘導」にならないよう注意する
オープン質問は「相手を評価しない」「相手が自分の言葉で語れる」という安心感を生みます。評価的な質問は無意識に圧力や緊張感を与えるため、注意が必要です。
●例
✕「あの会議、大変だったでしょ?」(相手の感情を決めつける)
〇 「あの会議、雰囲気どうでした?」(相手の視点に委ねる)
4-3. 「共感コメント」で会話を深める
会話の中で「すごい」「偉い」などの評価語を多用すると、知らず知らず上下関係が強調されることがあります。とくに職場では、年齢や立場、世代の違いによって「褒められること=おかしい」と思う人がいたり、逆に「もっと声をかけてほしい」と主張する人がいたりと、感じ方には差が出ます。雑談の場では、「相手を評価する」よりも「相手の話を受け止め、共感する」姿勢が大切です。共感コメントは、相手が「自分の話をちゃんと聞いてくれている」と感じるきっかけになり、さらに話したい気持ちを引き出す効果があります。
●ポイント
「そうなんですね」「それは大変でしたね」と相手の気持ちを受け止める
共感の言葉に一言添えると会話が続く
評価語(すごい、えらいなど)を減らす
共感コメントは「相手の努力・気持ち・状況」を一度受け止めること。相手を“承認”するニュアンスと近く、相手の自己肯定感や信頼感を高める効果があります。
●例
✕「そんなの簡単だよ!」(相手の努力を軽視する印象)
〇 「それは大変でしたね。無事終わって良かったです」(共感+結果を一緒に喜ぶ)
4-4.「信頼につながる雑談」にするための工夫
雑談は「単なる会話の時間」ではありません。日頃から雑談を通じて信頼関係を育むことが、いざというときの相談しやすさにつながります。しかし、職場では『なんでもハラスメント』と見なされるのでは……と不安を感じ、話しかける側が萎縮してしまうケースもあります。雑談は単なる時間の消費ではなく、信頼の土壌を耕す大切な営みです。職場という職の場で「安心して話せる」空気を作るために、日頃から“雑談の種”をまき続ける姿勢が大切です。
●ポイント
小さな雑談を積み重ねることで信頼が育つ
相談の「入口」としての雑談を意識する
無理に深い話題に踏み込もうとしない
雑談の目的は「親しさを強調すること」ではなく、「相談できる空気感」を少しずつ作ることです。「なんでも話していいよ」という言葉だけでなく、日頃からの関わり方が心理的安全性を支えます。
●例
✕ 無言で過ごす/「何かあったら言ってね」と言うだけ
〇 「最近忙しいですよね。何かお手伝いできることありますか?」(軽い話題+相談につながる雰囲気)
5.『なんでもハラスメント』を防ぐ職場文化の作り方
5-1. 管理職だけではできない、“相談できる空気”を育てる文化の必要性
『なんでもハラスメント』という言葉に表れるように、職場では「どこまでがハラスメントか」の線引きがますます難しくなっています。管理職個人の努力だけで全てをカバーするには限界があり、むしろ「相談できる空気」を職場全体で育てることが求められます。社員一人ひとりが「これっておかしいのでは?」と思うときに声を上げられる風土がなければ、問題は見過ごされがちです。
安心して意見を伝え合える環境は、単にハラスメント防止にとどまらず、組織全体の心理的安全性を高め、エンゲージメントや生産性の向上にもつながります。人事部門や経営層が「文化づくり」に主体的に関わることで、初めて「個人任せ」の限界を超えることができます。企業の規模や職種、社員の歳や代など背景が異なる中で、多様な視点を反映した「自分たちの職場に合う」ルールや対策を整えることが必要です。
たとえば、こんな課題はありませんか?
「相談窓口はあるが利用されていない」
「ハラスメント対策をしているのに、“安心できない”という声が消えない」
「管理職が何が正解かわからないと萎縮している」
こうした現状は、「相談できる空気」という土台がない限り改善が難しいのです。必要なのは、単なるマニュアルや解説ではなく、実践的で自分ごととして捉えられるルールや仕組み。会社全体で共有する“相談しやすさ”の文化が、企業にとって持続可能な強さにつながります。
5-2. 組織全体で“安全な雑談”を守るガイドラインの設定
安全な雑談は人それぞれの感覚や意識に委ねられることが多い領域ですが、それだけでは不十分です。企業として「どのような会話が望ましいのか」「どんな言動がハラスメントにつながるのか」について、具体的なガイドラインを定め、全員が共通理解を持つことが不可欠です。単に「これはおかしい」「それはやりすぎだ」といった個人の主張に頼るのではなく、組織全体で合意形成することが重要です。
しかし、ガイドラインづくりは簡単ではありません。「厳しすぎて会話が萎縮する」「抽象的すぎて役に立たない」など、バランスの取り方に悩む企業は少なくありません。年齢や価値観の違い、役職や職務内容によって感じ方に差が生じるため、「何を避けるべきか」という線引きは一筋縄ではいかないのです。
そこで有効なのが、外部の専門家による対策支援です。第三者の視点を入れることで、自社の状況に即した実効性の高いルールや仕組みを作ることができます。過去の事例や他社の成功例・失敗例を解説してもらうことで、「なぜこのルールが必要なのか」を具体的に理解しやすくなります。外部の支援を活用しながら、社員一人ひとりが「自分も声を上げていい」と思う、そんな風土づくりを進めていきましょう。
5-3. 職場文化をアップデートする――“仕組み”で支える安全な雑談
「安全な雑談」を人それぞれの努力に任せるのではなく、会社として“仕組み”で支えることが、文化づくりの要です。ハラスメント防止や心理的安全性の向上は、単にルールや研修を導入するだけではなく、日常的な接点や対話の機会を意図的に設計することから始まります。上から「こうすべき」と押しつけるだけでは反発する社員も出てくるため、実効性ある対策を講じるには、現場に合った工夫が求められます。
①学びの機会を提供する
心理的安全性を高めるためには、社員一人ひとりが成長できる環境が不可欠です。個々が学び、意見を交換できる場があることで、相互理解が深まり、信頼が育まれます。単に知識を増やすだけでなく、自由に声を上げ、自分の主張を伝えられる場が、職場の風通しを良くします。
●定期的な勉強会・ナレッジシェア会
部門横断的に社員が自分の知識や経験をシェアする場を設けることで、日々の業務で埋もれがちな小さな気づきや成功の事例を共有できます。「自分も話していい」という意識が育つと、職場での会話が活性化し、立場や歳の差に関係なく意見交換ができるようになります。
●リーダーシップ研修
管理職やリーダー層向けの研修を通じて、コミュニケーションスキルや心理的安全性の重要性を学んでもらいます。リーダーが率先して実践することで、「上司には言いにくい」という空気や、若手が萎縮して意見を控えてしまう状況を防ぎ、自然に相談や意見が出せる雰囲気をつくります。
●コミュニケーション研修
社員全体に向けたコミュニケーション研修では、効果的なフィードバック方法や効果的なコミュニケーション術を学びます。「どんなことでも話せる」関係性を築くためには、単に「聞く」姿勢だけでなく、相手を尊重しながら自分の考えを伝える力が必要です。こうした場を通じて、『なんでもハラスメント』と捉えられかねない誤解を減らし、安心して話せる土壌を育てます。
②つながりを強化する
「つながり」こそが、企業文化の基盤であり、社員間の信頼を育てる重要な要素です。特に、リモートワークも一般的に取り入れられ、物理的な距離が生じやすい今、心のつながりを意識的に築くことが、心理的安全性を高めるための大切な対策になります。つながりが希薄になると、ちょっとした発言が『なんでもハラスメント』と受け取られるリスクや、意見が言いづらくなる萎縮感につながることもあるため、意識的な取り組みが求められます。
●シャッフルランチ
定期的に社員をランダムに組み合わせてランチやカジュアルな会話を楽しむ場を設けることで、普段接点のないメンバー同士のつながりが生まれ、横の連携が強化されます。こうした場では、年齢や役職にとらわれず「おかしいと思ったことも気軽に声に出せる」「立場を越えて意見を主張できる」といった空気を育むことができます。
●リバースメンタリング
上司と部下が対等に意見交換できる場をつくるリバースメンタリングも効果的です。上司の立場から「最近の子たちの考え方は分からない」と感じる場面もあるかもしれませんが、若手世代の意見や感覚を知ることで、世代間のギャップを埋め、意見を言いやすい関係性を築けます。多様な世代の声を尊重する姿勢が、『なんでもハラスメント』を未然に防ぐ文化につながります。
●社内イベント・交流会
例えば、会社全体で行うカジュアルなイベント(スポーツ大会や趣味を共有する会など)を定期的に開催することで、部署や役職に関係なくリラックスした関係性を築けます。こうした場では、ふだん関わりの少ない職種や世代の異なる人同士が交流でき、互いの「主張」や価値観を理解するきっかけにもなります。雑談の中で「それ、おかしいと思う」という率直な声が自然に出せる関係性を作ることが、ハラスメントを未然に防ぐ対策としても有効です。
③安心して話せる場を作る
社員が自由に意見や不安を話せる場を作ることは、心理的安全性の礎です。特に『なんでもハラスメント』と過度に恐れて萎縮することなく、安心して意見を言える場があることが重要です。オープンで信頼できるコミュニケーションを育むために、誰でも安心して参加できる環境を提供する必要があります。
●相談のハードルを下げる職場文化
上司や経営層が積極的に社員の声を聴く体制を作ることは、「企業としての信頼」を築く大切なアクションです。日頃から「相談していい」「話していい」というメッセージを出し続けることで、社員は萎縮することなく、感じた違和感や「おかしい」と思うことを言いやすくなります。
●1on1ミーティング
定期的に個別面談を実施し、業務やキャリアに関する相談を気軽にできる場を用意することは、個々の悩みや要望の早期発見に役立ちます。実際の事例をもとにした解説を取り入れることで、管理職側も「どこまで話していいか」「どこからがハラスメントか」という線引きを学び、適切に対応できる力を養えます。
●カジュアルな会話の時間(カジュアル朝礼や雑談タイム)
固い業務のやりとりから離れて、ちょっとした雑談を促す場を提供することは、自然なコミュニケーションの練習の場にもなります。世代を超えて、上司も部下も歳の差を気にせずフラットに話せる機会は、『なんでもハラスメント』への過剰反応や萎縮を防ぐ助けになります。
これらの仕組みは、一度導入すれば終わりではなく、運用しながら自社に合う形にブラッシュアップしていくことが重要です。形式だけにとどまらず、「場があるからこそ自然に雑談が生まれる」「話せる機会があるから相談につながる」という状態を目指す必要があります。こうした取り組みを通じて、「会社に相談できる」という信頼感が積み重なり、ハラスメントリスクを低減する健全な職場文化が育まれていきます。
6.まとめ:『なんでもハラスメント』を防ぐために、管理職と組織が取り組むべきこと
近年、ちょっとした言動でも、ハラスメントにつながる可能性がある風潮が広がっています。管理職が部下に「最近どう?」と気軽に声をかけることすらも、ハラスメントと見なされるリスクがあるため、コミュニケーションを取ること自体に萎縮してしまう人も増えているのではないでしょうか。しかし、だからといってコミュニケーションを避けることが最善策ではありません。むしろ積極的に関わることが『なんでもハラスメント』という極端な環境を打破する鍵になります。日頃から「相談していい」「話していい」というメッセージを発信し続けることが、周囲との信頼関係を築くための大切な対策なのです。
『なんでもハラスメント』を防ぐには、管理職だけではなく会社全体での取り組みが不可欠です。職場におけるハラスメントの基準は人それぞれ異なり、歳の違いや立場、経験による認識の差もあります。だからこそ、組織全体でハラスメント防止の対策を共有し、正しい知識を持つことが重要です。具体的な事例を用いた解説を行い、共通理解を深める機会を作ることが求められます。
また、「学び」「つながり」「安心して話せる場」という3つの軸で施策を考えることが、職場における心理的安全性を高める鍵となります。定期的なイベントや仕組みづくりを通じて、社員同士がリラックスして意見を交わし合い、主張を遠慮なくできる雰囲気を整えることが大切です。企業文化を変革するには、一度きりの活動ではなく、継続的な努力が必要です。外部の専門家やコンサルタントの支援を受けながら、組織全体で取り組むことで、より効果的に心理的安全性を高め、健全で風通しの良い職場文化を築くことができるでしょう。
あなたの職場でも、安心して雑談できる関係性を築きませんか?カルチャリアのセミナーや研修を通じて、ハラスメントの線引きやコミュニケーションのコツを学び、職場の信頼関係を強化していきましょう。
シェア:
Send Us A Message