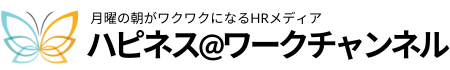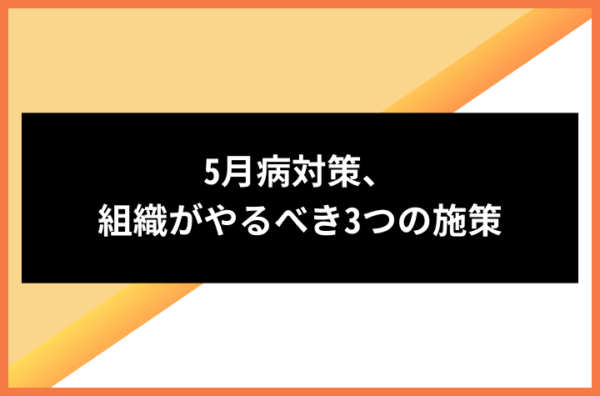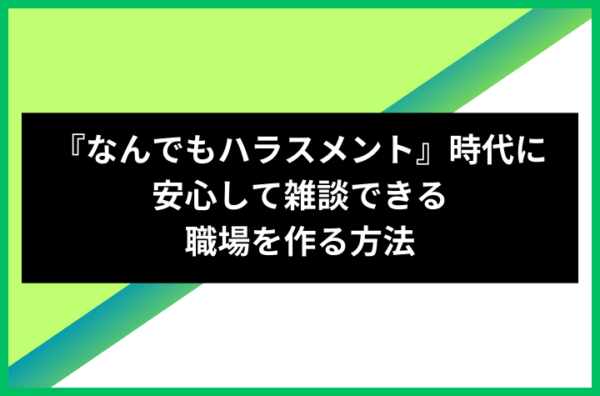動機という名の怪獣を飼いならして社員のモチベーションを向上させる
「モチベーション」。これさえあれば何でもできる、そう思いながら私たちは生きていませんか?小学生の夏休みの宿題からオリンピックのメダルレースまで、人の可能性を向上させるための最強の能力として。しかし、どの会社でも、社員のモチベーションが上がらないという悩みを抱えており、社員のモチベーションを向上させ、高い状態を維持させていくための、さまざまな取り組みが行われています。今回のコラムでは、社員のモチベーション向上を「おとぎ話の架空の怪獣」のように捉えて考えてみるという新しい方法をご紹介します。誰も本物を見たことがない、でもきっといる。そして飼いならせれば、素晴らしいことを起こしてくれる、社員のモチベーションが向上するに違いありません!
・社員のモチベーションが低く、効果的なフィードバックや目標設定に悩んでいる人事マネージャー
・社員のやる気を引き出すのが難しく、個々に適切なアプローチができていない経営者
・限られたリソースを最大限に活用したいがモチベーションを高める方法がわからないリーダー
💡こんな方におすすめです!
目次
1.モチベーションの重要性とその役割
あなたは「モチベーション」をどのようなものだと思っていますか?
モチベーションは単なる「やる気」を超え、私たちが目標を達成するための推進力そのものです。会社においては、社員一人ひとりのモチベーションが組織全体の生産性や成果に直接影響を与えるため、その重要性は言うまでもありません。モチベーションが高い社員は、目標に向けて自発的に行動し、課題を乗り越えるエネルギーを持つ傾向があります。一方で、モチベーションが低下すると、業務効率や成果が下がるだけでなく、職場の雰囲気やチーム全体の士気にも悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、モチベーションは個人の自己実現に深く関わっています。心理学者マズローの欲求階層説によれば、人間は基本的な生理的欲求や安全欲求が満たされた後、自己成長や自己実現を求める段階に進みます。この自己実現の欲求を満たすためには、適切な目標設定やフィードバックが必要であり、これを支えるのがモチベーションの役割です。
企業のリーダーや管理職にとって、モチベーションを高める環境を整えることは重要な課題です。たとえば、社員一人ひとりの価値観やスキルを理解し、それに合った目標や挑戦を与えることで、彼らの潜在能力を引き出すことができます。また、成果に対する公正な評価や感謝の言葉は、モチベーションを維持する上で非常に効果的です。
モチベーションは短期的な成果だけでなく、長期的な成長にも関わる重要な要素です。企業が持続的な発展を目指す上で、社員のモチベーションを高め、それを維持する戦略は欠かせません。
2.社員のモチベーションが向上しない理由とは?
社員のモチベーションが低下する理由はさまざまですが、その多くは環境や取り組み方の改善で解決することができます。本章では、代表的な原因とその対策について解説します。
2-1.やりたくない仕事や好きではない仕事
当たり前のことですが、「やりたくない仕事」や「好きではない仕事」に直面すると、誰でもモチベーションが下がるものです。このような状況では、社員が仕事に意義を見いだせなくなり、生産性も低下してしまいます。この課題への対処法として、まず社員がその仕事を「なぜこの仕事をする必要があるのか」を理解できるように説明することが重要です。仕事の目的や組織全体への貢献を明確にすることで、社員がやりがいを感じられる可能性が高まります。また、業務を分担したり、社員の得意分野を活かせるタスクを割り当てることで、適性に合った仕事環境を整えるのも効果的です。
2-2.目標や明確な理由がないこと
人は目標があるとき、そこに向かって努力する意欲が湧きます。しかし、目標や仕事の意義が不明確だと、モチベーションを感じにくくなるのも事実です。
企業は、社員一人ひとりが「自分の役割と目標」を明確に把握できるよう支援する必要があります。たとえば、SMARTゴール(具体的、測定可能、達成可能、関連性がある、期限が明確)を活用して、目標設定をするとよいでしょう。また、目標が大きすぎる場合は、それを小さな段階的な目標に分けることで、進捗を実感しやすくなり、モチベーションの維持につながります。
このように、モチベーションが上がらない原因には、仕事そのものや目標設定の問題が含まれることがわかります。これらを適切に対処することで、社員のやる気を引き出し、組織全体のパフォーマンス向上につながるでしょう。
3.社員のモチベーション向上のための3要素
社員のモチベーションを引き出し、維持するためには、単なる外的動機付けだけでは不十分です。モチベーション研究の第一人者であり、『モチベーション3.0』などの著書で知られるダニエル・ピンクの理論に基づき、内的動機付けを高める3つの重要な要素、「自立性」「成長」「目的」を解説します。
3-1.自立性(Autonomy)
自立性とは、自分のやり方で仕事を進める自由があることを意味します。社員が自分の裁量で意思決定できる環境は、モチベーションを高める重要な要因となります。たとえば、業務の進め方やスケジュールに柔軟性を持たせることで、社員は自分の仕事に対する責任感や満足感を感じやすくなります。
企業が自立性を推進するためには、過剰なマイクロマネジメントを避け、社員に信頼を置くことが不可欠です。自分で選択したと感じられる仕事は、モチベーションを高める大きなきっかけとなるでしょう。
3-2.成長(Mastery)
成長とは、スキルを磨き、自己能力を向上させる過程で得られる達成感を指します。社員が「自分は成長している」と実感できると、仕事への情熱や意欲が大幅に高まります。これを実現するためには、適切なチャレンジを提供することが必要です。例えば、業務に新しい課題を取り入れたり、学びの機会を設けたりすることで、社員は自己成長を実感できます。また、努力や進捗を認めるフィードバックも、成長意欲をさらに高める重要な要素です。
3-3.目的(Purpose)
目的は、「自分の仕事が社会や組織にどのような価値をもたらしているのか」を理解することによって生まれます。仕事の意義を感じられると、社員のやる気は自然と高まります。
企業は、社員一人ひとりが自分の仕事が組織や社会全体に与える影響を理解できるよう支援することが求められます。たとえば、定期的に会社のミッションやビジョンを共有し、社員の役割がそれにどう貢献しているかを伝える場を設けることが効果的です。
4.社員の幸福とモチベーション向上の深い関係
社員が職場で幸福感を感じることは、モチベーション向上に直結します。幸福感は、ただの感情ではなく、個人の生産性や創造性をアップさせ、組織全体の活力を引き出す原動力となります。この章では、幸福感を高めるための4つの重要な場面について解説し、モチベーション向上に繋がる環境づくりを提案します。
4-1.社員の成長実感
人は自分が成長していると感じると、幸福感が高まり、次のステップに進む意欲が湧きます。新しいスキルを学ぶ機会や挑戦的なプロジェクトに取り組む場面を設けることで、社員は達成感と自信を得られます。
●取り組み施策例:定期的なトレーニングやキャリア開発プログラムの提供。社員が目標を達成した際には、成果を称える仕組みを導入します。
4-2.良好な人間関係でモチベーションアップ!
職場での人間関係は、幸福感に大きな影響を与えます。信頼できる同僚や上司との良好な関係があると、ストレスが軽減され、モチベーションも向上します。
●取り組み施策例:チームビルディング活動の実施や、社員同士が気軽に意見交換できる場の提供。オープンなコミュニケーション文化を育むことも重要です。
4-3.社会的な意義を感じる
自分の仕事が社会や組織にどのような貢献をしているのかを実感することで、幸福感が高まります。意義を感じられる仕事は、社員の内的動機付けを強化し、持続的なモチベーションに繋がります。
●取り組み施策例:組織のミッションやビジョンを定期的に共有し、社員がその一部であると感じられる機会を提供します。
4-4.ワークライフバランスを保つ
仕事とプライベートのバランスが取れていると、幸福感が高まり、ストレスが軽減されます。適切な休息を取ることで、社員はリフレッシュし、仕事へのエネルギーを取り戻すことができます。
●取り組み施策例:フレックスタイム制やリモートワークの導入、有給休暇の取得を促す制度など、柔軟な働き方を推進します。
社員の幸福感は、モチベーションを自然に引き出す鍵となります。「成長」「人間関係」「意義」「バランス」という4つの場面を重視し、それぞれに適した環境を整えることで、個人と組織の両方にとってポジティブな成果を生み出せます。
合わせて読みたい!
公平な評価でエンゲージメント向上!組織力を上げる評価者研修とは?
5.アイデンティティとモチベーションの相関関係
アイデンティティとは、自分自身をどう認識し、他者と区別するかという自己認識であり、仕事や組織における役割に直結しています。自分というアイデンティティの自己認識があってはじめて、モチベーションが機能します。この章では、アイデンティティとモチベーションの関係を探りながら、日本と海外の企業文化の違いに触れ、個人の特性を尊重したマネジメント方法を解説します。
5-1.アイデンティティがモチベーションに与える影響
従業員が自分の役割や価値を認識し、それに誇りを感じると、仕事へのモチベーションが自然と高まります。一方、自分のアイデンティティが尊重されていないと感じると、モチベーションが低下し、仕事の成果にも悪影響を及ぼします。例えば、自分の専門性や個性が活かせるプロジェクトに携わることで、社員は達成感や充実感を得られます。また、評価が公平で透明性のある仕組みで行われる場合、社員は自身の役割をポジティブに捉えやすくなります。
5-2.日本と海外の企業文化の違い
日本企業では、しばしば「組織の一員であること」が重視され、個人のアイデンティティよりもチームや会社全体の目標が優先される傾向があります。そのため、同僚や上司と一致団結して目標を達成することに価値を置きますが、個人の自由や選択肢が制限される場合もあります。一方、海外の企業文化では、個人のスキルやキャリア志向が尊重されるケースが多く、個人がキャリアプランを主体的に描き、それに基づいた評価や昇進が行われる文化が根付いており、社員が自分のアイデンティティを活かして働ける環境が整えられています。
5-3.社員の特性を尊重したモチベーションの引き出し方
組織として社員のアイデンティティを尊重し、個性を活かす職場環境を作ることは、モチベーション向上に直結します。以下のポイントを意識した取り組みが有効です。
●パーソナライズされた目標設定
社員ごとに異なる強みや関心を考慮し、それに合った目標を設定することで、やる気を引き出すことができます。
●多様性を尊重する文化の醸成
異なる背景や考え方を持つ従業員を受け入れる姿勢を示し、多様な意見を尊重することで、社員の自己肯定感がアップします。
●キャリアの選択肢を広げる
社員が自分のキャリアプランに沿った道を選べるよう支援することで、長期的なモチベーション維持が可能になります。特に若手社員にはキャリアパスが見えるように環境を整えることが大切です。
社員のアイデンティティを理解し、尊重することは、組織の活力を引き出すうえで欠かせません。特にグローバル化が進む中で、日本と海外の文化的な違いを理解しつつ、社員一人ひとりの特性に応じたアプローチを採用することで、個人と組織の双方にとってより良い成果を得ることができるでしょう。
6.社員のモチベーションを「おとぎ話の怪獣」と捉えるアプローチ
他社の事例やさまざまな施策に取り組んでいるものの、なかなか社員のモチベーションが向上せず、生産性がアップしないこともあるでしょう。その場合、少し目線を変えたモチベーションを「おとぎ話の怪獣」と捉えるアプローチをご紹介します。モチベーションを「おとぎ話の怪獣=得体のしれないもの」として捉えることで、その捉えどころのない性質をより具体的に理解しやすくなります。見えないけれど確実に存在するこの力を正しく扱えば、驚くべき成果を生み出すことができます。
6-1.見えないけれど存在する「怪獣」
おとぎ話に登場する怪獣は、目に見えませんが、その物語の主人公たちの「動機」となり、そして怪獣なしでは物語は進んでいきません。まさにモチベーションも見えない怪獣です。目には見えなくても、確かにそこにあり、そして個人や組織の行動を支える重要な力となります。
6-2.怪獣を「飼いならす」方法
怪獣を飼いならすには、その性格や習性を理解し、適切に扱うことが必要です。同じように、社員一人ひとりのモチベーションの引き金を見極め、それに応じた働きかけをすることで、その力を引き出すことができます。たとえば、挑戦を好む人には新しい機会を与え、安定を求める人には安心感のある環境を整えるのが効果的です。彼らの怪獣をうまく使いこなすことで、最大の利益を生むことができるのです。
6-3.暴れさせないための配慮
怪獣が暴れると街が破壊されるように、モチベーションの低下は組織全体に悪影響を及ぼします。大きな力を持つモチベーションだからこそ、正しく使わないと暴力的、攻撃的になり、本人だけでなく周りにも被害を及ぼしてしまうのです。それを防ぐには、目標達成を称え怪獣をケアしたり、適切なコミュニケーションで、個人の怪獣が今どのような状態であるのかを知ることが効果的です。
6-4.奇跡を生む可能性
適切に向き合えば、怪獣は力強い味方になります。モチベーションも同様に、困難を乗り越え、創造的な解決策を生み出す原動力となります。人が何かを達成するのは、モチベーションがあってこそです。怪獣をうまく飼いならし、使いこなすことで、大きな成果を期待することができます。
7.知っておきたい!社員のモチベーション向上戦略と事例
社員のモチベーションを高めるためには、単に報酬や福利厚生だけに頼るのではなく、個人のアイデンティティや特性を尊重した育成策を立てることが欠かせません。企業が長期的にモチベーションを維持・向上させるためには、社員が働きやすい環境を提供し、内的動機を引き出す施策を実施することが求められます。このセクションでは、モチベーション向上に役立つ実践的なアプローチを紹介します。
7-1.社員の特性を反映した目標設定
社員一人ひとりが自分の強みや価値観に沿った目標を持つことが、モチベーションの向上に大きくつながるのです。企業は、社員の特性や希望を反映させた目標設定をサポートし、個別対応することが重要な役割です。社員が自分で目標を設定できると、仕事への意欲が高まります。例えば、OKR(Objectives and Key Results)や個別面談などの活用が効果的な方法とされています。会社から一方的に与えるのではなく、社員自らが目標設定をすることで、彼らのモチベーションを上げることができます。社員が自ら重要な目標を定められる場を提供し、そして彼らの考えを知る機会を作りましょう。
事例:目標設定を通じて社員が自分の成長を実感できるように、個人のキャリアパスや専門性を考慮して目標を策定します。たとえば、営業職の社員には販売目標だけでなく、顧客関係の強化を含めた目標設定を行い、個々の価値観に合った成果を重視します。
7-2.フィードバック文化の構築
大きな成果を目指すだけではなく、小さな成功体験を積み重ねることがモチベーションの維持に効果的です。小さな喜びを感じることで、その気持ちをまた体験するために、人のモチベーションは上がります。
日々幸せに生きるためにも、必要なことの一つです。そのため、社員のモチベーション維持のためには、定期的で建設的なフィードバックが不可欠です。評価制度が透明で、公正であることを確認するだけでなく、フィードバックを通じて社員の成長をサポートすることがモチベーションに大きな影響を与えます。上司や同僚からの建設的なフィードバックは、社員が成長を実感し、自信を持つきっかけとなります。そして、ポジティブなフィードバックだけでなく、改善点を指摘するフィードバックも、公平かつ具体的に行うことでモチベーションアップに繋がります。正しくフィードバックをすることが必要なので、研修等で体系的に学ぶのも一つです。
事例:定期的な1on1ミーティングや、360度評価制度を導入し、社員の成長を支援するために具体的なフィードバックを提供します。また、フィードバックの際には改善点だけでなく、良い点も積極的に伝えることで社員の自己肯定感を高めます。
7-3.社員の自立性を重視する
社員が自分の働き方や仕事の進め方に自由を感じると、その自立性がモチベーションを高めます。企業は過度な管理を避け、社員が自分のペースで成長できる環境を提供することが求められます。そして個人だけでなく、チームとしての成果を共有し、称賛することで、職場全体のモチベーションが向上します。そして、「互いに称え、祝うことができる環境」を作ることも、社員のモチベーションを高めることにつながります。
事例:フレックスタイム制度やリモートワークを導入し、社員に柔軟な働き方を提供します。自分のペースで仕事を進める自由度が高ければ、社員は自発的に業務に取り組み、モチベーションも高まります。
7-4.仕事をする意義や目的を共有する
社員が自分の仕事に対して明確な目的を持つことができれば、その仕事に意味を感じ、モチベーションが高まります。企業は、業務の背景や目標を社員にしっかりと伝え、社員が企業のビジョンに共感できるような環境を作りましょう。また、仕事の終わりに、その日達成したことを振り返る習慣をつけると、小さな成功体験が積み重なり、やる気の源泉となります。できたことにフォーカスすることで自己肯定感を上げ、明日の活力になります。
事例:定期的に全社ミーティングを開催し、会社のビジョンや社会貢献活動について社員に共有します。また、社員が自身の業務がどのように企業全体に貢献しているかを理解できるよう、業務の意義や目的を明確に伝えることが重要です。
7-5.ワークライフバランスの推進
社員が職場での幸福感を感じるためには、仕事と私生活のバランスを適切に取ることが不可欠です。適切な休養と柔軟な働き方を提供することが、長期的なモチベーション維持に繋がります。
事例:有給休暇の促進や、業務負担が過度にならないような調整を行うことで、社員がリフレッシュし、再度エネルギーを持って業務に取り組むことができます。企業は、過剰な労働を防ぐための仕組みを整えることが求められます。
このように、企業がモチベーション向上のために実践するべき戦略は、社員個々の特性やアイデンティティを尊重し、その人らしさを活かすことが基本です。目標設定、フィードバック、自立性の確保、目的の共有、そしてワークライフバランスの推進といった実践的な施策を通じて、社員が「働きたい」と思える環境を作り上げることがカギとなります。これらは前出、第4章の幸福度に共通する内容です。ポジティブな習慣の形成、自発性を引き出す仕組み、小さな成功の積み重ねが、社員幸福度と、やる気、組織全体のパフォーマンス向上に繋がるでしょう。
合わせて読みたい!
週休3日制で生産性は変わる?!メリットや導入ポイントを解説
8.まとめ:社員のモチベーションを向上させるために
いかがでしょうか?幸福度とモチベーションの共通点やすべての要素に「個人」という存在が軸になっていることにお気づきでしょうか?自分というアイデンティティの自己認識があってこそ、モチベーションが機能します。モチベーションは目標達成を助ける推進力であり、生産性や成果に直結します。社員がモチベーションを高く保つためには、自己成長を支える目標設定やフィードバックが重要です。「モチベーション」という概念を「おとぎ話の怪獣」に例えるなら、それをうまく飼いならし、社員一人ひとりのやる気の引き金を見極めて適切に働きかけることで、その力を引き出すことができます。
モチベーションが低下する原因には、やりたくない仕事や目標設定の不明確さが挙げられます。これを改善するためには、仕事の意義や目標を明確にし、社員の適性に合った環境を整えることが重要です。そして、モチベーションを引き出すための要素は「自立性」「成長」「目的」であり、社員が自分のやり方で仕事を進め、成長を感じ、仕事に意義を見出すことが士気向上につながります。
また、幸福度とモチベーションは密接に関連しており、社員が成長を実感し、良好な人間関係や意義を感じることで、やる気が上がります。社員のアイデンティティもモチベーションに大きな影響を与えます。個々の役割や価値が尊重される環境を作ることが、モチベーションを維持する鍵となります。
カルチャリアでは、職場の幸福度を高める研修や、従業員幸福度を測る「ハピネスサーベイ」などのサービスを提供しています。従業員の幸福度を測ることで現状を把握し、現在の職場に何が必要かを知り、適切な施策を講じることが大切です。モチベーションや社員幸福度、その他職場でのお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。
シェア: