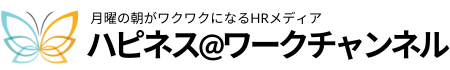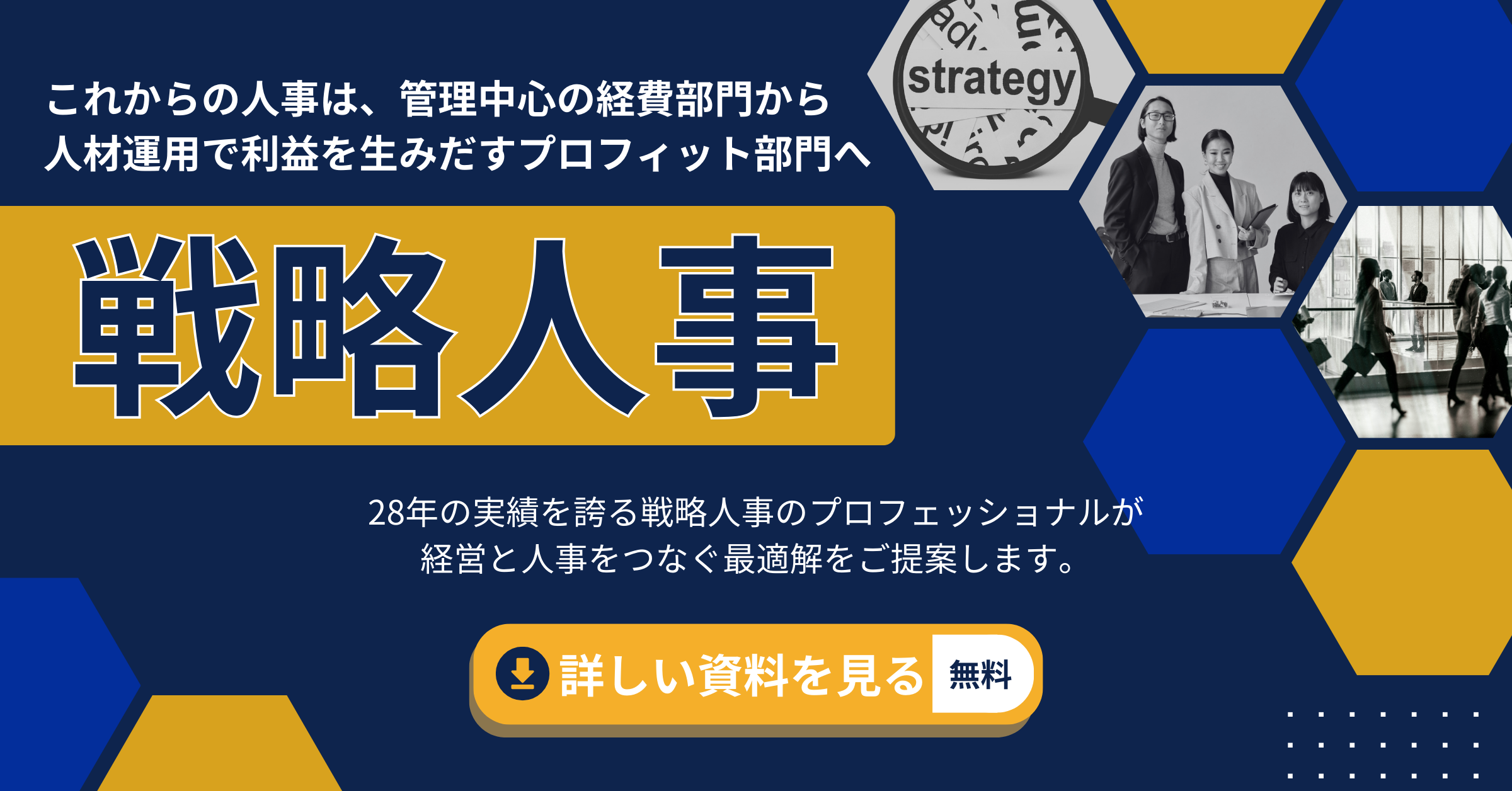組織改革の進め方を学ぶ!成果を上げるための実践的アプローチとは
組織改革の進め方に頭を悩ませる経営陣や人事部門の担当者は多いものです。カルチャリアではコンサルティングでさまざまな企業の組織改革や組織開発に携わってきましたが、効果的な組織改革の進め方の肝となるのは、明確なビジョンと実践的なアプローチです。本記事では、長年の組織開発経験から得た知見をもとに、組織改革を進める際の重要ポイントをお伝えします。社員の意識を変え、組織の仕組みを見直すことで、人事制度を再構築し、企業の風土を変えていくための具体的な進め方や方法論、考え方を解説します。よくある課題への対処法も交えながら、理論的なフレームワークを実務に落とし込む方法もご紹介。組織のあるべき姿を明確にし、社員一人ひとりが当事者意識を持って参加できる改革の進め方を学びましょう。これからの時代に求められる、働きがいのある職場づくりのヒントが見つかるはずです。
・少しでも早く組織改革を進めたいが、頭を悩ませる経営陣
・組織改革を進めているが何につまずいているのかわからない人事部門の担当者
・組織改革のために、どんな進め方が有効か情報を集めている方
💡こんな方におすすめです!
目次
1.あなたの会社の組織改革、順調に進んでいますか?
4月になり、新たな期がスタートしたこのタイミングで、組織改革を検討し始めた会社や、具体的に組織改革がスタートした会社もあることでしょう。組織改革は、業務運営で浮かび上がってきた課題に対処していくだけでなく、会社のさらなる発展のために組織体制の構造や役割、運用の方法を変える手段でもあります。また、環境の変化による組織改革の必要性を感じている経営陣も多いでしょう。
しかし、組織改革の進め方は一筋縄でいくものではありません。実際に大企業においても組織改革が運用に乗った後に失敗した例があります。富士通の事例を挙げてみましょう。1993年に他の企業に先駆け、日本で初めて管理職を対象にした成果主義を導入した富士通。その後、管理職だけでなく全社員も対象となり年功序列制度は廃止という、当時は革新的な人事制度改革として大注目されました。しかし、運用が開始されてから現場から多くの不満の声があがり、社員のモチベーションも下がる一方。結果的に会社の成長を見据えたはずの制度が足を引っ張り、業績も低下。その後成果主義は廃止されたという経緯があります。
組織改革の進め方において“確実に失敗する”ということを念頭においている経営陣はそう多くはありません。かねてから問題になっている事柄を解決すべく組織改革の運用も始まった、もしくは滑り出しはよかったので、もう大丈夫と考えているようであれば、その組織改革は前途多難です。
2. 組織改革が失敗する「進め方」4つの原因
では、組織改革が失敗する原因とは何でしょうか。下記は組織改革の進め方においてよくある失敗の例です。
2-1.幹部が勝手に進める、一人の意見が強すぎる
社長の鶴の一声で組織改革が進んでいませんか。狭い会議室に幹部だけが集まって組織改革の中身を決めていませんか。トップダウンで突然明日からやりますと現場に投げても、現場はただただ混乱するだけです。経営陣や管理職、一般社員など、おのおのの立場によって組織に対する考え方や意見、課題は異なります。特定の階層の目線だけで進められた組織改革では途中で頓挫してしまい、うまく機能しない可能性大です。各階層から広く考えや課題を吸い取り、組織開発の観点から意識的にプロセスを設計しましょう。
2-2.導入したものの、うまく運用にのらない宝の持ち腐れ事案
改革という言葉だけが先走ってしまい、現場が置き去りにされる典型的な例です。例えば、ある営業部では今までExcelで顧客管理をしていた。しかし、誰かがExcelを使っているとそのブックを開けないので不便、入力の手間がかかるなどという声があがっていたため、業務効率を上げるために、CRMを導入した。しかし、操作がむずかしくて誰も使いこなせず、結局今までのExcelを使い続けている……というような、結果的に現場の社員が使いこなせないというケースはよくあります。組織改革の進め方を見直し、運用が開始されても改善の兆しが見えないので、ふたを開けてみたら全く機能していないということはありませんか?
2-3.社員の意見を聞きすぎる
社員の声ばかりを聴きすぎてしまうと、逆に会社として目指すべき方向からずれが生じてしまうので、気をつけなければなりません。昨今、社員の幸せは会社の発展につながるという、従業員満足度(ES:Employee Satisfaction)の重要性について注目されています。社員の声を集めることで、社員に対して会社は社員のことを考えているというパフォーマンスになり社員満足度もあがるかもしれませんが、社員満足度に固執することで本来の目的を見失うことのないよう組織風土とのバランスを見極め、組織改革の土台となる課題を抽出しなければなりません。
2-4.適切な判断基準がないために、課題が見えてこない
組織改革を進めるうえで、物事を評価・判断するための適切な基準が定まっていないと、何が本当の課題なのかを見極めることができません。他社や業界の状況、自社の実力とのギャップを把握できてこそ、取り組むべきテーマが明確になります。しかし、その前提となる基準自体がズレていたり曖昧だったりすると、的外れな課題設定につながり、結果として改革も空回りしてしまいます。
3. 組織改革の進め方で、よくある勘違い
特に上層部において、下記のような意識が根底にあると、組織改革の失敗につながる恐れがあります。
3-1.社員からの理解を得るのは運用開始後ではなく、組織改革を始める前
会社として目指すビジョンを明確にすること。これは、組織改革を成功させるために重要な一手です。まずは組織改革を始める前に、会社としてこれから目指す姿と、なぜ目指すのかという目的、その展望を明らかにし、全社的な共感や納得を得ることが最初の一歩。社員の共感や理解が組織改革への関心や意識につながり、組織改革の原動力になりますので、事前に社員に対して説明の場を設け、組織改革の進め方や会社の考え、方向性、本気度を伝えるようにしましょう。
また、組織改革を進めていくにあたり、組織改革へのモチベーションをアップすることも必要です。その環境づくりとして、ビジョンに共感できるメンバーを採用したり、インセンティブによって社員のモチベーションを作り出すという方法もあります。また納得できないという社員には退いてもらうような措置も場合によっては必要になります。
3-2.主役は社員。上司の自己満足で終わらせない
組織改革を進めても、上層部の”組織改革をやった”という絵に描いた餅のような事案になっていませんか? 結果的に部下の困りごとが解消されないのであれば、実績にはなりません。また、運用が開始されたのでもう大丈夫、やることはやったから終わりというのは単なる自己満足でしかありません。運用が始まった後にもやるべきことはあります。開始後も経緯を見守り、成果が安定して出るようになるまで組織改革という勝負は続きます。組織開発の観点から、継続的な見直しと改善が重要なポイントです。
合わせて読みたい!
女性活躍にうんざり?社内の本音と現実~本当の意味での多様性とは~
4. 組織改革を成功させる進め方、4つのポイント
では、組織改革を成功させるためには、どのような進め方が有効なのでしょうか。
4-1.プロジェクトチームの立ち上げ
幹部が頭を突き合わせて組織改革の構想を練るのではなく、組織改革のプロジェクトチームを立ち上げ、手順を検討していくことが、組織改革の有効な進め方です。
プロジェクトチームの人選としては、
●先頭に皆を引っ張っていけるリーダータイプの人材
●変化に強いイノベータータイプの人材
●信頼度の高い課長・部長レベルの人材
などの選出をお勧めします。
その理由として、
①新しいものを作り上げるプロジェクトのため、既存の枠組みの中で駒を動かすタイプでは、行き詰ってしまう可能性がある。
②改革を行うということは、現状を壊して新しいものに作り替えることなので、現状維持を支持する抵抗勢力が必ず現れます。そのため、現場の理解やリアルな根回しが必要になるので、各部門との調整を担う役回りや、ファシリテーターとしてプロジェクトを導く管理職レベルの人材の登用が求められる。
③部長以上になると、現場との目線が異なりプロジェクトメンバーと合わない可能性が大きくなる。
メンバー選びは組織改革プロジェクトの進め方に大きく影響しますので、慎重に行う必要があります。人事制度との整合性や各部の協力体制を構築することも重要なポイントです。
4-2.短期・中期・長期のKPI設定
次に挙げる5つの項目に沿ってKPIを設定してみましょう。組織改革のゴールを明確にすることで、目標(ゴール)に対して集中でき、パフォーマンス測定も可能にします。また、組織改革メンバーも自分に何が期待されているのか、目標を見失うことなく何に向かって努力すべきなのかが分かるようになります。これも組織改革の進め方における重要なポイントです。
●KPI設定のポイント
①「何を(成果指標)」「どれだけ(成果水準)」行うかを明確にする
② 成果指標は測定可能なものとする
③ 成果目標はマネージャーと社員の話し合いで合意しているか
④ 成果目標は現実的に達成可能か確認すること(ストレッチ目標)
⑤ 成果目標は期日を明確にしているか
●KPI設定の例
✖【悪い例】プロジェクトがうまく進むように努力し、チームに貢献する
〇【良い例】プロジェクトにおいて9月末までにコスト削減○○百万円を実現する
悪い例では、「努力」や「貢献」など、聞こえはよいですが具体的ではなく、単なる努力目標をにおわすような、ぼんやりとした表現が並んでいます。良い例では、具体的な金額や期日などの数字が提示されているので、後々パフォーマンス測定もできます。このような具体性も組織改革を成功に導く重要な進め方です。
合わせて読みたい!
企業でも個人でも!今日からできる生産性向上のための実践ガイド
4-3.組織改革の進め方における課題抽出
業務報告で上がってくる数値や評価面談、1on1ミーティング、サーベイなどから課題を抽出していきましょう。数字や文書などで見られるものがあれば、組織改革を実施する際に周囲への説得材料にもなります。”なんとなくうまくいかない”という、直感的にもやもやするような進め方であれば、組織改革へ向けて舵を切らずに待ちましょう。一呼吸おいて、我々のような専門家へ相談するのも一つの手段です。状況を整理し、何が問題なのか、組織改革の明確な進め方を示してくれます。なんでも社内でやろうとはせず、外部から組織開発の専門的な知見を活用することは、より効果的な課題解決が期待できます。
合わせて読みたい!
人事BPOで企業成長を加速!導入のメリットと成功の秘訣
4-4.ベータ版を走らせ、問題・課題を明確にして修正を行う
運用を始める前に必ずテスト期間を設けることは、組織改革の進め方として非常に効果的です。運用にのせても失敗する可能性はあるということを念頭に置き、まずはベータ版(テスト)から始め、そこで失敗したこと・浮かび上がった課題を見直し、修正するPDCAサイクルを繰り返してプロジェクトの精度を高めていくことで本格運用後の大規模なイレギュラーや問題を回避しやすくなります。匿名の目安箱・意見箱のようなものを設置して意見を収集することも改革の精度アップにつながります。このようなフレームワークを活用した組織改革の進め方の例は、多くの成功事例でも紹介されています。
5.まとめ
組織改革とは、企業が人事や組織開発を見直し、社員の意識改革を通じて新たな目的に基づく制度や企業文化を築く取り組みです。そして、会社という組織を構成している社員の意識改革とも言えます。自社の人事部が独自で動いたり、外部のコンサルタントが推奨するフレームワークや手順を活用することで、抱える課題を解決し、部門間の連携を強化することが可能です。
しかし、人の意見や考えはすぐに変わるものではありません。組織改革を始める前に、まずは社員に対して組織改革を行う理由やビジョンの方向性、実際の進め方などを説明・理解する機会をしっかり設けることが重要です。社員の共感を得ることがよいプロジェクトチーム発足の鍵になります。
また、KPIを設定し、ベータ版でテストと修正を繰り返し精度を高めてから本格運用することで、大きなトラブルを回避しやすくなるでしょう。適切な進め方で、ぜひ組織改革を成功へ導いてください。組織開発の理論に基づいた人事制度の見直しや組織体制の再構築が、企業風土の改善と社員の意識向上に大きく貢献する事例は数多く紹介されています。明確なビジョンと具体的な目的、そして効果的なフレームワークを活用することで、組織改革の進め方は必ず成功に結びつくでしょう。
日々の業務で人事は手いっぱい、組織改革を進められるような人材を採用したくても難しいなど、人員が確保できない、でも課題はたくさん……。そんな待ったなしの状況にある場合は、ぜひ私たちのような専門家を頼ってください。外部からの専門的な知見を活用することは、より効果的な課題解決が期待できるだけでなく、専門領域の知見を社内に蓄積していくことも可能です。カルチャリアでは、まず組織診断で状況を整理し、何が問題なのか、そのボトルネックに則した施策をご提案します。
シェア: